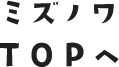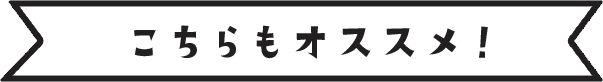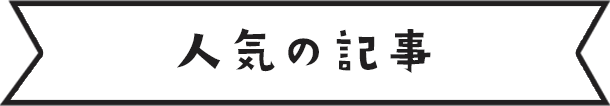電気主任技術者が知るべき昇柱訓練とは!?~フルハーネスの取り付け方から器具の役割・点検まで~
- 転職×電験
- 2025.04.08 更新日:2025.07.02
外部委託で、保安業務従事者もしくは電気管理技術者として働こうとしている皆さん!
電柱に登って作業をすることがあるって知っていました…!?
意外に知られていない、この「昇柱作業」。
月次点検や年時点検と違ってあまり目立たないですが、昇柱作業はPASの操作・点検などを目的に行う電気保安業務の一つ!
今回は、カフェジカスタッフが電柱に昇る訓練「昇柱訓練」を初めて体験した様子をお届けします。
外部委託に必要な作業について、簡単ではありますがイメージを持っていただけたらと思います!
▼動画はこちら!▼
【電気主任技術者が知るべき昇柱訓練】
カフェジカもっちと水島とで、初めて電柱に昇る訓練をしてみた!in 三重
1.今回、昇柱訓練を行う現場は…
今回はなんと!
出張カフェジカということで三重県の津に伺わせていただいております。
電気管理技術者のわんさん(鳥谷尾さん)の事務所で昇柱訓練ができるということで、このたび津市までお邪魔しているのです!
今回訓練を行うのは、もともと消防の詰所だったところをわんさんが買い取った際にあった電柱。
訓練用などの用途で残していたものだそう。

なんと!
昇柱訓練のYouTubeを見て「自分もやってみたい!」ってなった場合、わんさんに直接連絡でもいいんですか…??
はい、大丈夫です。
三重の仲間は、実際に訓練に来ています。

電柱にのぼる訓練をできる場所は数少ないので、すごく貴重な体験になるんじゃないかと思っております!
わんさんに加えて、電柱に何度も登った経験のあるあきら博士にアドバイスや注意事項を教えてもらいながら、今回の昇柱訓練を進めていきます!
2. フルハーネスの取り付け方

ではこれから、昇柱訓練をさせていただきたいので、器具の取り付け方から教えてください!
今回の高所作業訓練において身体に装着するフルハーネスなどの装備器具。
従来は「安全帯」という名称で使われていましたが、2019年2月から施行された法律改正で、器具の名称が変更されています。
■従来の「安全帯」に含まれていた器具
① 胴ベルト型(一本つり)
② 胴ベルト型(U字つり)
③ フルハーネス型(一本つり)
参考
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
このうち、①③のみを新しい名称である「墜落制止用器具」として使用することができます。
そして、②は「ワークポジショニング用器具」とみなされ、「墜落制止用器具」には含まれないため、②のみで高所作業を行うことはできなくなりました。
今回の訓練では、③フルハーネス型を使用していきます。
加えて今回は、「ランヤード」という部分が前側から出ている作りになっている電力会社仕様のフルハーネスを使用します。
通常、背中側からランヤード(ショックアブソーバーとフックが付いている器具)が出ているのが一般的です

頭からかぶり、フルハーネスを装着していきます。
全体的に締まるように、長さを調整していきます。

墜落制止用器具は、万が一落下して器具にぶら下がったときに全体的に荷重が分散するような構造になっているのです。
続いて、「ワークポジショニング用器具」をフルハーネスの上から取り付けていきます。
「ワークポジショニング用器具」は「墜落制止用器具」としては認められていないため、現在はフルハーネスとの併用が必須です。
続いて胴綱を、「ワークポジショニング用器具」にある四角形の金具に取り付けます。
胴綱には「伸縮器」が付いており、握るとロープが緩まり、手を離すとロープが固定されます。
以前は伸縮器の辺りに工事用フックが付いていたのですが、今はないため、「ワークポジショニング用器具」の金具に取り付けておきます。
胴綱のもう片方のロープは、電柱に巻き付けるのに使用します。
使う方のロープは、「ワークポジショニング用器具」の右側にあるD環にかけておきます。
実際に使う際は、ロープがきちんとD環にかかっているかを目と耳で確認することが大切です。
D環がかかっていたら絶対に落ちることはないので、そのロープを利用しながら登っていきます。
「墜落制止用器具」はフルハーネスの胸の辺りにかけておきます。
すべてのロープをきちんと引っ掛けたら、準備は完了です。
金具を引きづることがないよう、それぞれのロープはそれぞれ器具に付いている金具に取り付けておきます。
3. 器具の役割
水島さんともっちが付けている器具は、墜落したときの安全器具(墜落制止用器具)と作業用の器具(ワークポジショニング用器具)の2つ。
墜落制止用器具
フルハーネスに付いているランヤード。
そのランヤードに付いている器具はショックアブソーバーと言い、万が一落ちたときの落下の力を弱める役割を持ちます。
これによって、墜落したときのケガを防ぐことができるのです。
ある一定の高さにならないとショックアブソーバーは有効にはならないものの、万が一の事故やケガを予防するための大切な装置となっています。
ワークポジショニング用器具
腰に装着した「ワークポジショニング用器具」。
昔は、高所作業のときに「ワークポジショニング用器具」しか使用していませんでした。
現在「ワークポジショニング用器具」は、あくまでも自分が作業するための器具であるという位置づけになっています。
墜落防止用の器具ではないことを覚えておきましょう。

電柱の高さ
現在の労働安全衛生法では、床の高さから2m以上である場合、高所作業になると決められています。
参考
労働安全衛生法令における墜落防止措置と安全帯の使用に係る主な規定|厚生労働省安全衛生部安全課建設安全対策室
この規定は、2mの高さよりも足がある位置が高くなったら必ず高所作業用器具を付けなければならない、ということを意味します。
高圧気中開閉器のロープは、大体3.5~4mくらいの場所に取り付けられています。
2mよりも高い位置となるため、高圧気中開閉器の操作は墜落制止用器具がなければできない、と言えます。
そして、訓練に使用する電柱に付いている2本目の足場釘。
そこに足をかけた瞬間に2mを超すため、高所作業となるのです。
電柱のチェック
訓練で使用する電柱は、コンクリート柱。
昔あった木柱と比べると腐食しにくいものの、コンクリート柱でも腐食する場合があります。
中の鉄筋に水気が入ると内部がふやけてしまい、コンクリートが剝がれてしまいます。
コンクリート柱でも、所々に穴が開いていたり、根本部分に強度がかかって割れている場合があるため、これから登ろうとするコンクリート柱が劣化していないかを事前に確認する「外観点検」を行います。
外観点検がOKだったら次に、電柱を登るための足場釘を確認していきます。
確認するのは、足場釘の向き。
「昇柱経路」と言い、電柱に登るための脚立の向きと足場釘の位置が一直線になっているかを確認します。
方向があっていないと、脚立から足場釘に乗り移るときに身体を90°回転させなければならず、危険です。

加えて、脚立をかけるときには段差がない所を選ぶのもポイントです。
また、脚立が壊れていないか、ロック機能が確実にかかっているか、脚立と電柱を固定ベルトを縛ってズレないか・外れないかについても、登り始める前に確認します。

足場釘が折れる恐れはないんですか?
足場釘が折れる可能性は、あります。
登っていくときに、手でつかんで足場を確認しながら進んでいくことがポイントとなります。
電柱を登るときは、とにかく【安全第一】でやっていくことが大切です。

4. 器具の点検と取り扱い方法
器具の点検

器具のフックに歪みがないか、ロープなどにほつれ・擦れがないか、などをはじめにチェックします。
ロープは、使用していくうちに擦り減ってきてしまいます。
たとえば、伸縮器が付いているロープが擦り減ってしまうと、中に織り込んである赤い糸が見えてくるようになります。
赤い糸が見えてきたら交換の時期、という目安があるため、ロープの擦れなどはきちんと確認することが大切なのです。
付け方の基礎
はじめに墜落制止用器具を、電柱に付いている頑丈で落ちないような金具に取り付けます。
このとき、焦らずに、確実に落ちないところに金具を取り付けるのが大切です。
このときも、目と耳で確認していきましょう。

墜落制止用器具はあくまでも、落下したときに助けになる道具。
そのため、作業中に墜落制止用器具およびショックアブソーバーに自分の体重をかけることは絶対にない、ということを理解しておくのが大切です。
金具を取り付けられそうな部分がない電柱の場合、足場釘の上側の電柱自体に墜落制止用器具を巻き付けて、下からフックをかけるようにします。

上からフックをかけると目で確認しづらく、中途半端に引っかかった状態になる恐れがあります。
フックは下からかけ、きちんとかかっているかを確認しましょう。

墜落制止用器具は命綱であり、作業するためのロープがワークポジショニング用器具となります。
ワークポジショニング用器具のロープを、電柱にぐるっと巻き付けるようにし、腰部分にある金具に取り付けます。
きちんと器具を付けられているかどうか、ロープに体重をかけて確認します。

墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具の両方を付けたら、電柱での作業に移ることが可能になります。
5. 昇柱訓練
いよいよ電柱に登っていきます。
脚立を使い、足場釘の上にワークポジショニング用器具を付けます。
このとき、2mの高さを超える前にワークポジショニング用器具を付けるということをお忘れなく!
フック取付のときには、声掛けも忘れず行いましょう。

ワークポジショニング用器具のロープを持ち、次の足場釘に引っ掛けながら登っていきます。
ポイントは右手・右足、左手・左足を同時に動かすこと。
右手でワークポジショニング用器具のロープを持ちながら、右足を次の足場釘へ、右手を次の足場釘へと移動させていきます。

墜落制止用器具をかけるときは、必ずワークポジショニング用器具の内側からロープを回して取り付けることも、大切なポイントです。
かなり訓練が必要だということ、分かりましたか?


めちゃめちゃ分かりました!
かなり訓練が必要な作業ですね…!
これでようやく、作業に取り掛かることができ、墜落防止もできる体制になりました。
実際の作業は、足場釘などから両手を離し、ワークポジショニング用器具に体重をかけた状態で行います。

電柱から降りてきて、脚立がある位置まで来たら、高所作業ではなくなります。
そうしたら、ワークポジショニング用器具を外します。
これを何回もやって、慣れることが大切です。
終わりに
月次点検や年次点検と違ってあまり目立ちませんが、昇柱作業はPASの操作や点検などを目的に行う電気保安業務の一つです。
近年は特に、外部委託業務を行うための実務経験年数が短くなり、必要書類も簡素化される動きとなりました。
これにより、選任やビル管理会社などで経験年数を積まれた方の電気保安業界への参入が大きく増えていくことが予想されます。
ただ、電気保安管理業務の実務知識を学ぶ機会はいまだ極端に少ないことから、外部委託従事者の技術レベルやお客様対応がおろそかになってしまう恐れが危惧されます。
だからこそ、あまり学ぶ機会のない昇柱作業を今回取り上げさせていただきました。
「自分も体験してみたい!」
「みんなで行く機会を作ってほしい!」
という方は、ぜひお気軽にお声をお寄せください。
▼ご連絡はこちら▼
【著者情報】
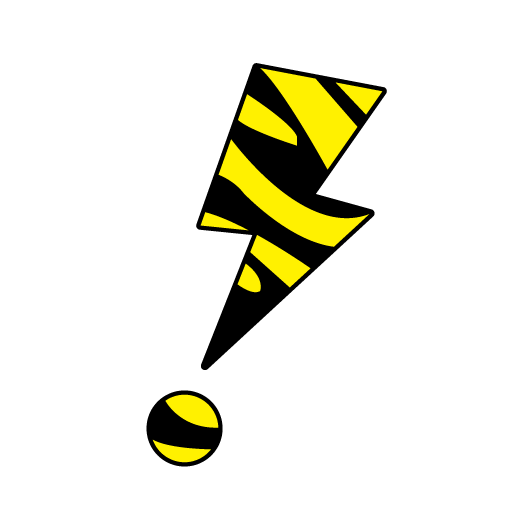
電気主任技術者メディア編集部
電験や実務など、「電気主任技術者」にまつわる情報に特化したメディアコンテンツ制作集団。
電気主任技術者専門の転職エージェント株式会社ミズノワが運営する「電気通信ピカリ」内の記事を執筆・発信中。
転職エージェントとして、求人案内総掲載数240件以上、求職者様の総ご相談者数2,500名を超える実績を持つミズノワ監修のもと、分かりやすくて面白いメディア運営を進めております。